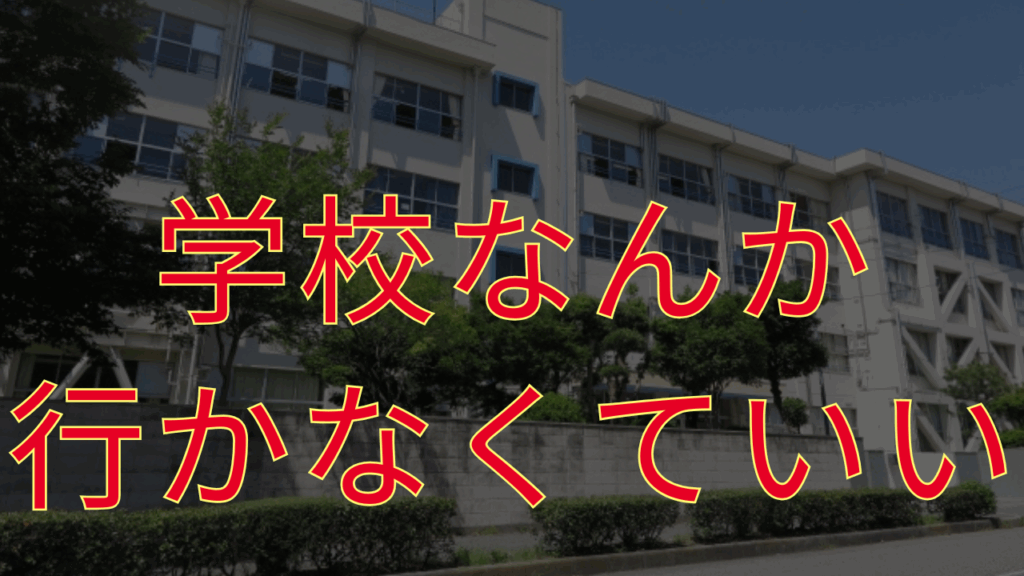
「学校なんか行かなくていい」
某元不登校ユーチューバーのようなことを言うようですが、私もこの考えには賛成です。

私自身も学校が大嫌いだったし、37歳になった今でも学校に行ったのは失敗だったと思っています。
この記事では、学校に行かなくていい理由、そして行かないメリットやデメリットなどをまとめてみました。
こんな人に読んでほしい
・現在不登校、もしくは元不登校の人
・学校が嫌い、もしくは嫌いだった人
・学校に行きたくないと悩んでいる学生
・学生時代が不遇で自殺志願を持っている人
・自分の子供が不登校という親
☆学校に「行けなかった」ではなく、「行かなかった」という選択ができる時代が訪れます。
子供の数は毎年減り続けているのに、子供の自殺者は年々増えています。
その事実に向き合い、この記事を書きました。
私は未来に向けて、この記事を届けたいなと思います。
1,はじめに

「当たり前」を疑うことで見えてくる世界があります。
1-1、「学校に行くのが当たり前」はもう古い
多くの人が「学校に行くのが当然」という価値観を当たり前に受け入れて育ちます。
幼稚園、小学校、中学校、高校、そして大学へと続くレールが、まるで社会への唯一の入り口であるかのように示されます。
しかしその「当たり前」は、誰にでも当てはまるわけではありません。
すべての人に「正しいこと」なんてありえないのに、学校に行くのが絶対正しいと決めつけるのはおかしなことです。
教育のあり方、学びの本質、そして現代社会で生きる上での必要な力というのを考えた時に、無理して学校に行く必要はないと確信を持つことができたので、そちらを解説していきます。
1-2、学校に行きたくない理由
・クラスメイトにいじめられている
・担任の先生とどうしても合わない
・ずっと座って授業を受けているのが苦痛
・勉強がとにかく嫌い
などなど、学校に行きたくない理由は様々だと思いますが、そんな人も今一度、本当にこれからも学校に通うべきなのか考えるきっかけにしてもらえれば幸いです。
そして、「学校に行かない」=「引きこもる」ということではありません。
「学校に行かない代わりに何をするか」というのが大事です。
2,学校というシステムの正体

学校と言うのは、子供の個性も特性も特徴も性格も全部無視して、同じことをやらせようとする環境でもあります。
そんな場所に、全幅の信頼をおいてもいいのでしょうか。
2-1、画一的に決められたカリキュラム
国語、算数、理科、社会などの決められたカリキュラムを、決められた時間に、決められた教室で受けるのが学校です。
集団行動が基本で、決められたルールの中で生活することになります。
これは近代国家が形成される過程で生まれた教育システムであり、「優秀な労働者」を育てるための仕組みとも言えます。
2-2,学校にある窮屈感の正体
19世紀以降の工業化社会では、規律を守り、効率よく作業できる人材が求められました。学校教育はまさにそのための装置だったのです。
つまり学校とは「個性を伸ばす場」というよりも、「社会に適応できる人間」を育てる場所だったと言えます。
そんな場所に閉塞感や疑問を持つのは当たり前です。
もしあなたの周りにその疑問を否定する大人がいるなら、そいつはあなたの人生を壊そうとする大人です。
もちろん読み書き計算などの基礎的な能力を学ぶという点で、学校教育は大きな意味を持つのは間違いありません。
しかしそれだけが学びではないはずです。
学校という場所は、時として子供の個性を殺す場でもあります。
3,教室の外にある学びの世界
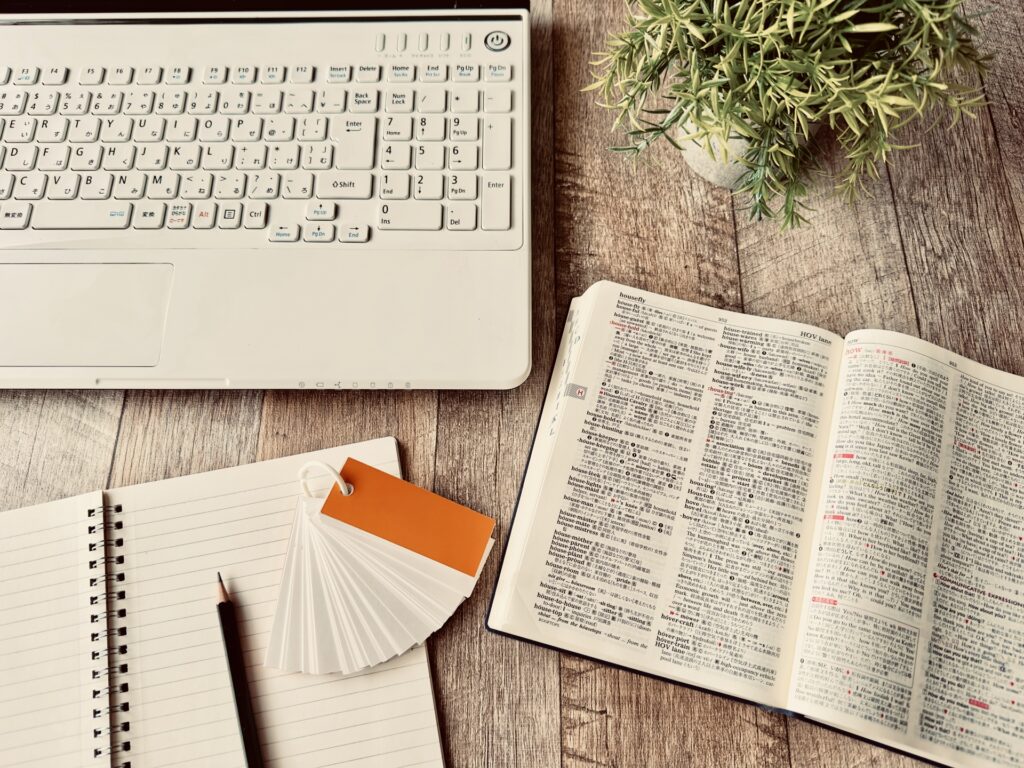
教室から飛び出してみることで、学びの場と言うのはたくさん見えてきます。
3-1,多様な学びの選択肢
今の時代、学びの方法は無限にあります。
少し恐ろしいことですが、インターネットを使えば誰でも世界中の知識にアクセスすることができてしまいます。
YouTubeで数学を学び、英語を海外の先生から習い、プログラミングをオンラインで実践することもできます。

私も最近、オンラインのプログラミング教室に通っていました
3-2,社会への入り口は学校からだけではない
実際、学校に通わずに自分で学び、自らの道を切り開いていく若者も増えています。
例えば、ITエンジニアやデザイナーの世界では、学歴よりも「何が作れるか」「どんなスキルがあるか」が重要視されます。
ポートフォリオ一つで企業と契約し、世界中のプロジェクトに関わることもできるわけです。
つまり「学校で学んでから社会へ」という一方通行な流れだけではなく、「社会の中で学び続ける」という逆のアプローチも可能になっているので、そういう選択を選ぶことも、これからの社会ではスタンダードになっていくかもしれません。
学校に行かない代わりにスキルを身に付けておけば、普通に学校に通っている人達よりも早く社会人としてスタートすることができるのです。
4,学校でしか得られないもの

学校に行かなくても学べることが多いように、学校に行ったからこそ得られるものもたくさんあります。
4-1,学校の意味
私も学校を全否定するつもりはありません。学校には学校にしかない価値があります。
たとえば、人間関係のトレーニング。
理不尽な上下関係や、集団の中での自分の位置づけ、友人との関わりなど、社会の縮図のような経験を積める場でもあります。
特別な才能やスキルがなく、やりたいこともそれほどない場合は、これらの経験を積んでおかないと、社会に出て困ることになるでしょう。
そして学生時代の友人は、一生の友となることも多いです。

人間関係は、苦手な人にはどうにもならない部分はあります
4-2,青春の1ページ
「何が得意か」「何が苦手か」といった自己理解を深めるきっかけにもなります。
クラブ活動、学園祭、部活動など、人生における一大イベントのような体験も、学校ならではです。
「青春」という言葉も、学生のためにあるような言葉なので、青春を味わえずに大人になると、その歪みがどこかで出てくることが多いです。

私は学校に行ってても、青春を味わうことはできませんでした
ただし集団生活が苦痛でしかない人にとっては、学校は「自己否定を強いられる場所」でしかないのも事実です。
繊細な子どもや、特定の環境に強いストレスを感じやすい子どもにとって、学校という場所が必ずしも成長を促す安全な場所とは限りません。
学校に馴染めないからと言って、「私はダメな人間なんだと自分を卑下する必要はまったくありません!
5,破綻しつつある学校システム

ものすごいスピードで色んなことが変わっていく現代社会で、学校というシステムが社会に追いついていない部分も多くあります。
その中でもとりわけ深刻度の高いいじめ問題に関しては、早急な対策が求められます。
5-1,深刻化するいじめ問題
SNSでの誹謗中傷、無視、仲間外れ、物を隠す、暴力などなど、昔より巧妙で見えにくい形になっているので大人も気付きづらく、よりいじめは深刻な問題となっています。
文部科学省の統計でも、いじめの認知件数は過去最高を更新し続けています。
昔と違って、ちょっとのことでも取り上げるようになったから数が増えたという見方もできますが、多くの学校でいじめというのは避けては通れなくなっているのは間違いありません。
それにも関わらず教室の中では「見て見ぬふり」がまかり通り、被害者だけが孤立し、傷ついていく現状があります。
そして自殺するまで追い込まれてしまうケースも増えています。

そうなるくらいなら、学校なんか行かない方がいいです!
5-2,「いじめ推進国家」となっている日本
なぜ子供がいじめをするのか。答えは簡単。大人がやっているからです。
ちょっとネットを開けばそこら中に暴言、悪口、罵詈雑言が書き込まれています。
その書き込みによって人が死のうがお構いなしです。
そしてテレビなどでも「炎上」を面白おかしく話しています。
「炎上」というのは、一人の人に大勢で寄ってたかって言葉の暴力を浴びせること。すなわち「いじめ」です。
そのいじめ行為がそこら中で横行しているのに、裁きを受ける人をほとんど見ることがありません。
大人はいじめを容認しています。
日本は国を挙げていじめを推奨している、いじめ推進国家です。
そういった大人の姿を見た子供が、いじめをしないわけがありません。
いじめを根絶するためには学校だけが変わっても意味はなく、社会全体が変わらなければいけません。
5-3,下がる教師の質
教師の質が下がるのは、なにも教師だけの責任ではありません
・モンスターペアレント
・厳しい指導を断罪する現代社会
・労働時間に見合わない賃金
・教師同士のいじめ
これらの要因によって真面目な教師ほど辞めてしまい、結果、質の低い教師や、経験不足の教師が増えてしまっています。
こんな環境で、教師もいじめ問題に真剣に向き合うことなどできません。
周りの大人が頼りにならない以上、子供だって自分の身は自分で守るしかなく、学校に行かないという決断も時には必要になってきます。
教師も自分のことで精一杯で、すべての子供に目を配るのは難しいです。
5-4,教師が学校以外の世界を知らない
一部の例外を除いて、基本的に教師と言うのは高校大学を卒業してそのまま教師となります。
バイトの経験などは多少あるでしょうが、教師は学校以外の社会を知りません。
そんな教師が、多様化していく社会に飛び込んでいく子供たちに的確な指導ができるかと言うと、正直疑問です。
これは教師が悪いというわけではないし、平成中期まではそれでも良かったのです。
ただ現代は目が回るほどに選択肢や考え方も増えたので、教師の持つ能力では子供を指導しきれなくなっています。
教師はただ勉強を教えるだけというスタンスでいいなら構わないのですが、残念ながら親や社会はそれを許してくれません。
教師にとって、教師の仕事がどんどん難しくなっているのは気の毒にも思います。
6,「学校に行かない」という選択肢の肯定

私が子供だった数十年前は、不登校は悪いことだと言われ、そう思っていました。
しかしこれからは、そんな考えも変えていきましょう。
6-1,不登校は悪いことじゃない
まだまだ「不登校」という言葉に対してネガティブなイメージがあるのが現代社会です。
しかし「学校に行かない=終わり」ではありません。
むしろ「学校に行かないからこそ見える世界」もあります。
子ども自身の興味や才能を最大限に伸ばすための、積極的な選択肢となり得るのです。
6-2,学びの選択肢はたくさんある
通信制高校やフリースクール、ホームスクーリング、オンラインスクールなどなど、学校に頼らない新しい学びの形は増えています。
大切なのは「学ばない」のではなく、「自分に合った学び方を選ぶ」ことです。
「学校に行かないこと」は逃げではなく、「自分の人生を自分で選ぶ」という、最初の一歩かもしれません。
学校に行かない方が、可能性が広がる子供も少なくないでしょう。
7,学歴社会の終焉とこれから
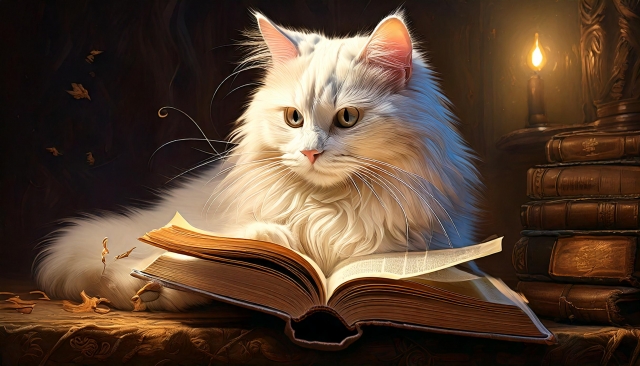
かつては「いい大学に入って、いい会社に就職する」というルートが人生の正解でした。
まだまだ学歴社会が根強いのも事実ですが、今はそんな状況も変わりつつあります。
7-1,知識偏重の教育と実社会の乖離
現代社会は急速に変化し続けているのに、学校のシステムはそれに追いついていません。
AI技術の進化やグローバル化の進展など、学校で学ぶ知識だけでは対応しきれない現実が広がっています。
知識の詰め込み型の教育は、思考力や問題解決能力、コミュニケーション能力といった、実社会で求められる重要なスキルを十分に育成できていないという現実は、多くの若者が社会に出て痛感しているでしょう。

学校で学んだことは、社会に出てほとんど役に立ちません
7-2,学校という閉鎖的な空間
学校は、ある意味で社会から隔絶された閉鎖的な空間です。
多様な価値観や考え方に触れる機会が限られ、社会の現実との間にギャップが生じることがあります。
社会に出る前に、学歴だけではなく、もっと多様な経験を積むことも重要です。
そして閉鎖的ゆえに子供の視野を狭めてしまい、同時に可能性も狭めてしまうことがあります。
7-3,好きや得意を生かせば道は開ける
YouTuber、フリーランス、個人起業家、投資家などなど、現代は「肩書き」よりも「成果」や「個性」が重視される社会へと移行しつつあります。
その意味では「学歴がすべて」の時代はもう古いと言えます。
学びは資格や卒業証書ではなく、「何を身につけたか」「何を成し遂げたか」で評価される時代です。
学校に行けばある程度決められたレールが敷かれますが、学校に行かないからこそ無限の可能性が広がっています。
8,「学校に行かない」という選択の課題と乗り越えるべき壁

「学校に行かない」という選択は多くの可能性を秘めている一方で、いくつかの課題も存在します。
8-1,社会的な理解と偏見
「学校に行かない」という選択は、未だに社会的な理解が得られにくいのが現状です。
「怠けている」「将来が心配だ」といった偏見を持たれることも少なくありません。
一定の学歴に満たない人は採用しないという企業もまだまだ多いのが現実です。
このような偏見を乗り越え、多様な教育のあり方が社会的に認知されるためには、情報発信や公的議論が不可欠になります。
そして個人的には、学歴のない発信力の強い人の出現によって、社会が変わっていくと予想しています。
8-2,学習の質の確保と自己管理能力
学校のような組織化された環境がない場合、学習の質をどのように確保するかが重要な課題となります。
家庭やオンラインでの学習においては、子ども自身の自己規律や動機付けが不可欠で、簡単なことではありません。
というより、子供だけでなんとかさせようとしても、不可能に近いはずです。
親や周囲の大人は子どもの自主性を尊重しながらも、適切なサポート体制を構築する必要があります。
プロの栄養士が一生懸命考えて作った給食も学校に行かなければ食べられず、家でそれだけの食事も用意しなければいけません。
すなわち親の負担が増すということで、共働きが主流の現代社会では難しいところでもあります。
8-3,社会とのつながりと孤立のリスク
学校は子どもたちが社会性を育む重要な場でもあります。
「学校に行かない」場合、社会とのつながりが希薄になり、孤立してしまうリスクも考慮しなければなりません。
ホームスクーリングのグループに参加したり、地域社会の活動に積極的に参加したりするなど、意識的に社会との接点を持ち続ける工夫が必要です。
特に同世代の友人や仲間との会話や交流が極端に少なくなると、それは社会に出てからも大きな弊害となって立ちふさがります。
どれだけ知識を入れてスキルを身に付けても、一人でできる仕事なんてほとんどありません。
8-4,進路選択の多様性と情報収集
学校には、進路指導の専門家がおり、進路に関する様々な情報を提供してくれます。
「学校に行かない」場合、進路に関する情報を自ら収集し、主体的に進路を選択していく必要があります。
キャリアカウンセリングを受けたり、様々な分野で活躍する人たちの話を聞いたりするなど、積極的に行動することが求められます。
自ら行動していかないと何も始まらないという状況は、子供にとってかなりハードルの高いことですが、学校に行かない以上は避けては通れません。
子供の頃から自己解決を繰り返してきた先には、あなたにしかないスキルが身に付いていると思います。
9,行かない勇気が人生を変える

「学校なんか行かなくていい」という言葉には反骨心や挑戦心が宿っているように、現状では半端な覚悟で選べる選択肢ではありません。
大切なのは他人の価値観に自分を当てはめることではなく、「自分はどう生きたいか」を真剣に考えることです。
子供がそこまで考えるのは難しく酷なことかもしれませんが、大人が決めた「学校」というシステムを避ける以上、自分で決めるしかないのです。
自分で決めた先に、「学校に行かない」という選択が未来を切り拓いていきます。
大人も「学校に行くのが当たり前」という固定観念を捨て、子供たちの多様な選択肢を尊重し、それぞれの可能性を応援していく社会を築いていく必要があるのではないでしょうか。