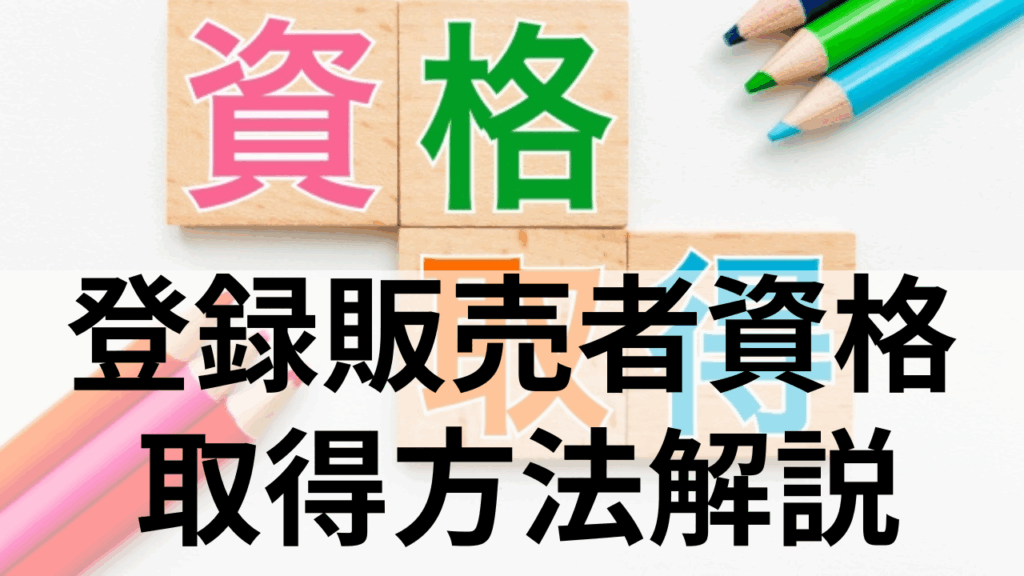

最近よく耳にする登録販売者ってどんな資格?
ドラッグストアで働くには必須なの?
難しそうだけど、どうやって勉強したらいいんだろう?
このように思っている方もいるのではないでしょうか。
登録販売者は身近にあるドラッグストアや薬局で、一般用医薬品(第二類・第三類医薬品)の販売を担う専門家です。
薬剤師が不在の時間帯でも医薬品の販売ができるため、地域医療において重要な役割を果たしています。
この記事では登録販売者資格の取得方法から試験の難易度、具体的な対策方法までを徹底解説します。
こんな人に読んでほしい
・これから登録販売者を目指す方
・資格について詳しく知りたい方
・資格マニアの方
こんな方たちは、ぜひ最後まで読んでいってください。
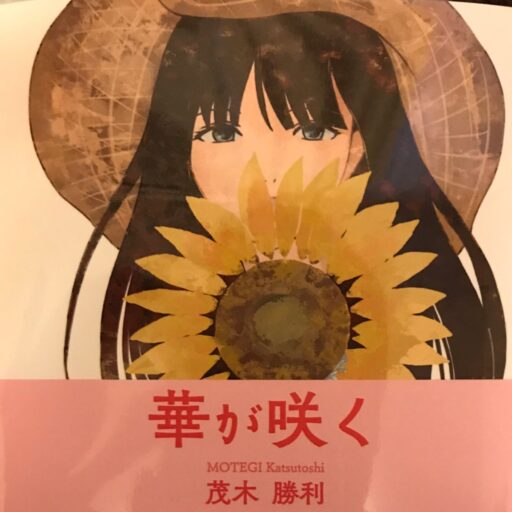
私は完全未経験の独学で合格したので、参考になるかと思います。
1,登録販売者とは何か?

まず登録販売者とは何か、概要や活躍できる場所などを解説していきます。
1-1,資格の概要
登録販売者は、厚生労働省が定める「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」に基づく公的資格です。
2009年に誕生し、薬剤師でなくても一部の医薬品を販売できるようになりました。
薬剤師が不在でも一般用医薬品販売ができる専門家として、薬局やドラッグストアからも注目されています。

登録販売者は国家資格じゃないの?
明確に「国家資格」を記載している文部科学省の「国家資格一覧」には、登録販売者は記載されていません。
ただ国家資格という言葉の定義が明確に定められていないので、登録販売者は「国家資格である」とも、「国家資格ではない」とも明言することは難しいというのが実情です。
それ故に、サイトやブログなど様々な媒体で見解が違います。
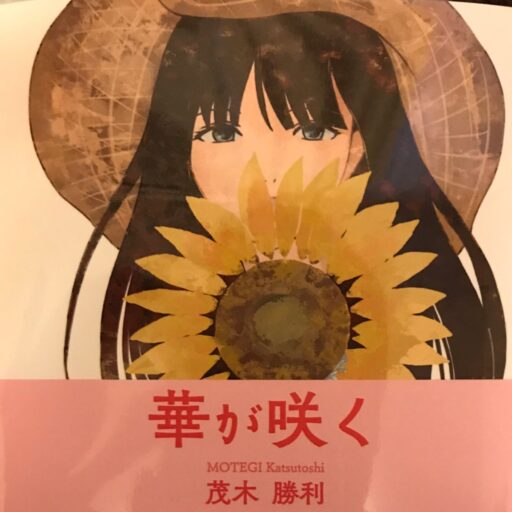
私も最初見たサイトに「登録販売者は国家資格」と書いてあったので、それを信用していました。
1-2,取り扱える医薬品の範囲
登録販売者は、第二類および第三類医薬品の販売が可能です。風邪薬や鎮痛剤、整腸薬、湿布など、日常的に使用される医薬品が中心となります。
調剤や第一類医薬品(例:ロキソニンS、ガスター10など)の販売は薬剤師のみが可能です。
一般用医薬品の9割以上が第二類以下の医薬品になるので、登録販売者が扱う医薬品は非常に多いです。
1-3,活躍の場
主に以下のような場所で活躍できます。
・ドラッグストア
・調剤薬局(OTC医薬品を扱う場合)
・ホームセンター
・コンビニエンスストア(医薬品販売許可を持つ店舗)
・ディスカウントストア
などがあります。
医薬品を扱う店舗が増えたり、病院に頼らず軽度な身体の不調は自分で手当てをする、セルフメディケーションの考えが浸透しているのもあって登録販売者の需要が尽きることは当分ないと言えます。
2,資格資格と試験概要

次に登録販売者資格を取得するためのステップと、試験の概要について解説します。
2-1,受験資格
登録販売者試験には、特別な学歴や実務経験は原則として必要ありません。誰でも受験することができます。
受験者数は年々増加しており、社会的なニーズを考えても、今後も増えていくことが予想されます。
2-2,試験の実施時期と場所
登録販売者試験は、各都道府県が年に1回実施しています。
試験の時期は都道府県によって異なりますが、例年8月から12月頃に実施されることが多いです。
試験会場も都道府県ごとに設定されます。
試験を受けられるのは基本的に年一回ですが、そこで落ちても、すぐに開催時期の遅い別の都道府県の試験に申し込めば、試験を受けることが可能です。
2-3,試験科目と出題範囲
登録販売者試験は、以下の5つの科目で構成されています。
第1章:医薬品に共通する特性と基本的な知識(20問)
医薬品の定義、剤形、吸収・分布・代謝・排泄、副作用、相互作用、安全性情報など、医薬品全般に関する基本的な知識が問われます。
第2章:人体の働きと医薬品(20問)
人体の各器官の構造と機能、主な疾病の原因や症状、予防などに関する知識が問われます。
第3章:主な医薬品とその作用(40問)
一般用医薬品として販売されている主な成分の作用、効果、副作用、使用上の注意などに関する知識が問われます。
第4章:薬事に関する法規と制度(20問)
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)や関連法規、医薬品販売に関する制度などに関する知識が問われます。
第5章:医薬品の適正使用と安全対策(20問)
医薬品の添付文書、リスク区分、情報提供、副作用報告制度、濫用・誤用防止対策など、医薬品の安全な使用に関する知識が問われます。
注意
出題範囲・問題数は全国共通ですが、地域によって午前・午後で出題項目が異なる場合があります。
受験される地域の過去問などで傾向をチェックするようにしましょう。
3,難易度と合格率
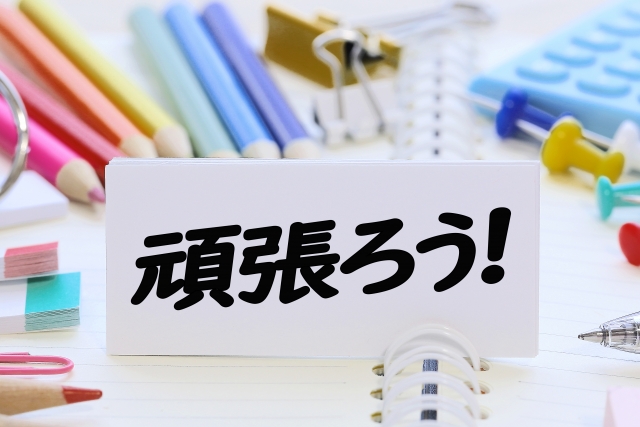
3-1,合格率
2023年の合格率は43,7%でした。
ただこの数値は都道府県によって大きく異なります。
例えば、2023年度の試験において最も合格率が高かった県は群馬県の55.2%でした。
一方、最も低かった県は高知県の21.4%です。その差は30%以上。
これはあくまでも2023年度だけを見た結果であり、都道府県別の合格率はその年によっても違いがあります。
3-2,合格基準
合格基準は、各都道府県によって若干異なる場合がありますが、一般的には以下の2つの条件を満たす必要があります。
総得点
全120問のうち、7割程度の正答率。
なので84点が合格に必要なラインとなります。
各科目
各科目で5割以上の正答率。
第4章が苦手で20問中8問しか正解できなかった。でも他の科目は満点だった。これでも不合格となります。
つまり全体の得点だけでなく、各科目で一定以上の点数を取ることが求められます。
苦手科目を作らず、バランスよく学習することが重要です。
3-3,難易度の実感値
未経験でも十分に合格可能なレベル
私も完全未経験プラス独学で臨みましたが、半年ほどの学習で合格できました。
医学・薬学の専門用語が多いため、最初は取っつきにくいと感じることもある
薬の成分名とか、ひたすら暗記しないといけないのは心折れるかと思いました。
記憶量が多く、丸暗記では対応しきれない分野もある
漢方とか量が多すぎて、全部記憶するのは無理です。
3-4,他の医療系資格との比較
医療系の国家資格としては、医師、薬剤師、看護師などがありますが、これらの資格と比較すると、登録販売者試験の難易度は低いと言えます。
登録販売者試験は一般用医薬品に関する基本的な知識が中心であり、受験資格に学歴や実務経験が問われないため、比較的挑戦しやすい資格と言えるでしょう。
4,効果的な勉強法と対策
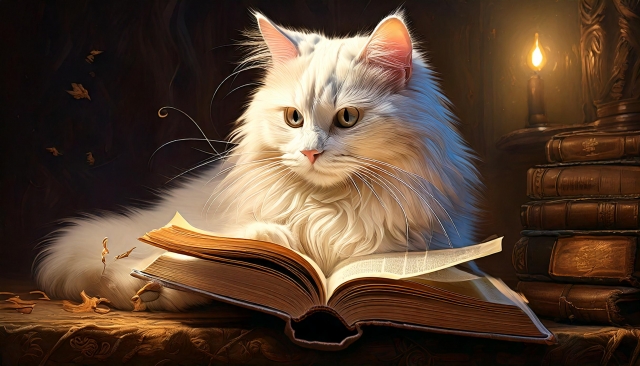
登録販売者試験に合格するための具体的な対策方法を解説していきます。
4-1,学習期間の目安
一般的には、3〜6ヶ月程度の学習期間を確保する方が多いです。
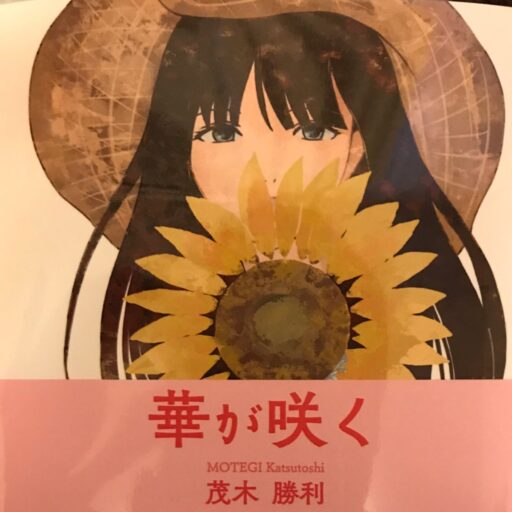
私も半年ほどの期間で合格しました。最初の3か月は慣らしで、後半3か月集中して勉強したという感じです。
4-2,試験対策の基本:過去問の活用
どの試験でもそうかと思いますが、登録販売者の資格においても、とにかく過去問を徹底的に解いていくということが重要です。
私も正直、勉強はほぼ過去問を解くことしかしてません。
過去問集のテキストが色々売っているので、私は2冊の過去問集を買い、正解率がほぼ100%になるまでやりこんで合格しました。
あとはネットで検索すると登録販売者試験の過去問が結構出ているので、そういったのも活用していました。
過去問の活用方法としては、
・解いたら必ず解説を読む
・間違えた問題をノートにまとめる
・模擬形式で時間を計って練習する
といったやり方が有効です。
4-3,ボイスレコーダーを活用
書くだけでは覚えきれないし、耳からも覚えたい。そう思ってスマホのボイスレコーダーも活用しました。
私は漢方を覚えるために使っていたのですが、漢方名と効能、使われている生薬などを音読して、それを録音しました。
そして車の運転中や空いてる時間に流して、音として脳に刻むという方法を取っていました。
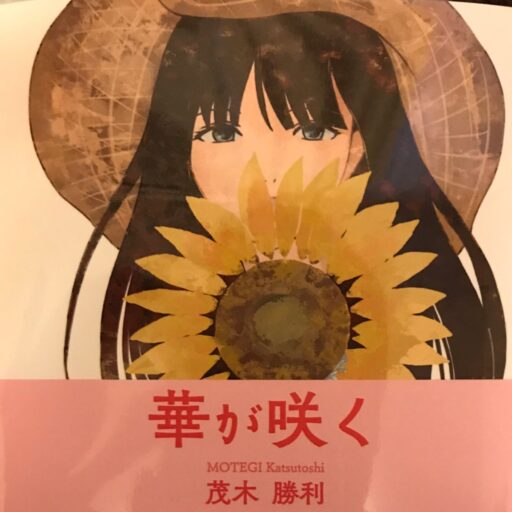
試験直前の、追い込み時にやっていた勉強法です。
4-4,通信講座・予備校の利用
独学に不安がある場合は、通信講座や予備校の利用も検討しましょう。
専門の講師による解説や、効率的なカリキュラムで学習を進めることができます。
コストはかかってしまいますが、その分後に引けなくなって勉強に集中できるということもあります。
5,合格後の流れ

見事試験に合格した後、登録販売者として働くにはどういう経緯を踏んでいくのかについて解説していきます。
5-1,合格後の手続き
試験に合格しただけでは、すぐに登録販売者として働けるわけではありません。
各都道府県の薬務課に登録申請を行う必要があります。
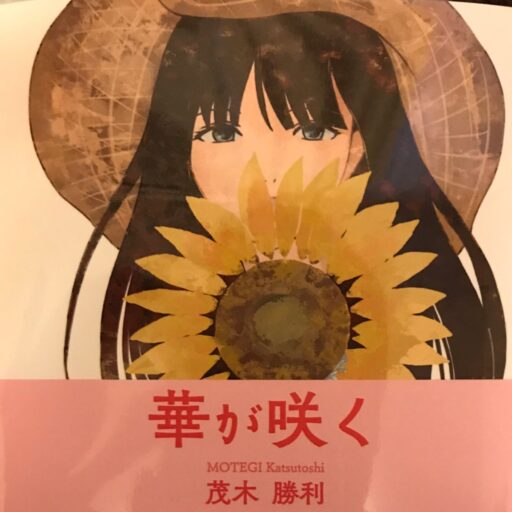
ただ私はこの申請を自分でやった記憶がないです。
おそらくですけど、登録販売者として働くお店に入った時に色々書類を書いたので、申請もお店の方でやってもらったような気がします。
5-2,登録販売者として働くには
登録販売者として独り立ちするには、原則「直近5年で通算2年分(計1,920時間)の実務経験が必要」という規定が設けられています。
直近5年以内であれば、資格取得前の実務経験も適応されますが、5年以上経過している場合は適応外になるので注意してください。
☆同じ店舗で月80時間以上勤務・計2年以上の実務経験がある登録販売者
正式な登録販売者として働くには、直近5年間に通算2年以上の実務経験が必要とされていますが、さらに以下の条件が含まれます。
・1ヵ月に80時間以上実働する必要がある
・同一月、同一店舗で働いた場合に実務経験として認められる
同じ勤務先で月に80時間以上勤務した場合のみ、登録販売者の実務経験として登録されます。
複数の勤務先を掛け合わせて同様の実働時間を稼いでも、同条件を満たしたことにはなりません。
☆一般従事者として正式な登録販売者の指導下で合計2年以上の実務経験がある
一般従事者として薬剤師、または正式な登録販売者の下で通算2年以上実務経験を積むことで独り立ちできます。
アルバイト、パート、正社員と、雇用形態はなんでも構いません。
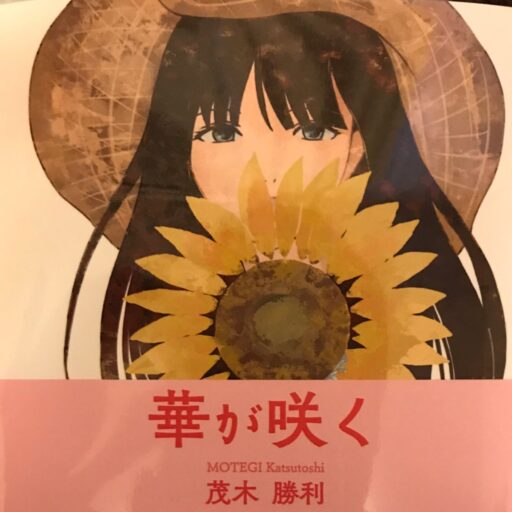
私は2年アルバイトして独り立ちした後に正社員になりました。
6,まとめ

登録販売者は未経験からでも挑戦しやすく、将来的にも需要が高い安定した資格です。
ドラッグストアや薬局をはじめ、様々な場所で活躍することができるため、就活にも有効な資格だと言えます。
専門的ではあるため最初は尻込みしてしまいますが、自分に合った方法で学習すれば、合格は十分に目指せます。
この記事で解説した学習方法や対策を参考に、効率的に学習を進め、登録販売者資格の取得を目指してください。
資格取得後のキャリアパスも視野に入れながら、読者の方の成長に繋がっていくことを願っています。
登録販売者は医薬品を扱う場所には必須の人材なので、この機会に是非、医療従事者の仲間入りをしてください。